設計者は誰?
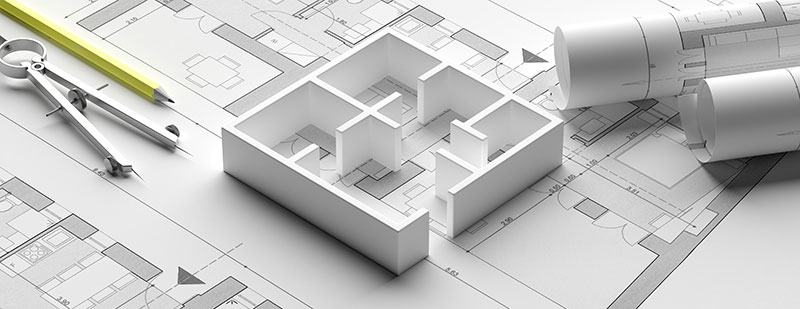
県庁の工務店向け研修会に参加しました
先日、鳥取県版構造計画ガイドラインについて学ぶため、県庁主催の工務店向け研修会に参加しました。
講師は構造塾の佐藤さん。また、島根の工務店・勝部建築さんの実際の工事現場の写真を見ながら講義を受けました。
現在、耐震等級3が必須とされる時代になっていますが、その達成方法に問題がある建物も少なくありません。
力技で基準をクリアしているものの、構造的に無理がある住宅が多く見受けられます。
例えば、直下率の悪い間取りになっているため、大きな梁を組むことで対応し、結果としてコストアップにつながっているケースが多いようです。
研修では、県庁の槙原さんからセミナー開催の主旨について説明がありました。
住宅政策課では、NE-STの申請を受ける際、提出された図面を確認していますが、「この建物の構造、大丈夫?」 と思うことが多々あるそうです。
実際、NE-ST申請には図面一式を提出するため、県内の建物図面データが大量に蓄積されています。
下手な工務店よりも経験知が豊富かもしれません。
弊社設計スタッフが取り組んでいる設計塾や構造塾の重要性を改めて認識しました。
大きな声では語られませんが、今回の講義では、住宅業界の「闇」の部分にもスポットが当たりました。
新築プランを作成しているのは誰なのか?
もしかして、設計の知識がない営業マンがプランニングをしているのではないか?
せめて二級建築士の有資格者であるべきです。
さらに理想を言えば、
・住宅設計に長年携わっているベテラン設計士
・多くの建物を見て経験を積み、日々勉強を続けている設計者
こうした人が設計に関わることで、より良い住宅が生まれます。
より良い住環境を提供するためには、「構造」「断熱」「耐久性」「空調」 を高い次元でバランスさせることが求められます。
さらに、それらを両立しながらも手の届く価格で提供することが重要です。
私たちは、経営の安定を図りながら、設計の試行錯誤を重ね、日々挑戦を続けています。
構造的に安全で、快適な暮らしを実現する家づくりに、これからも真剣に取り組んでいきます。